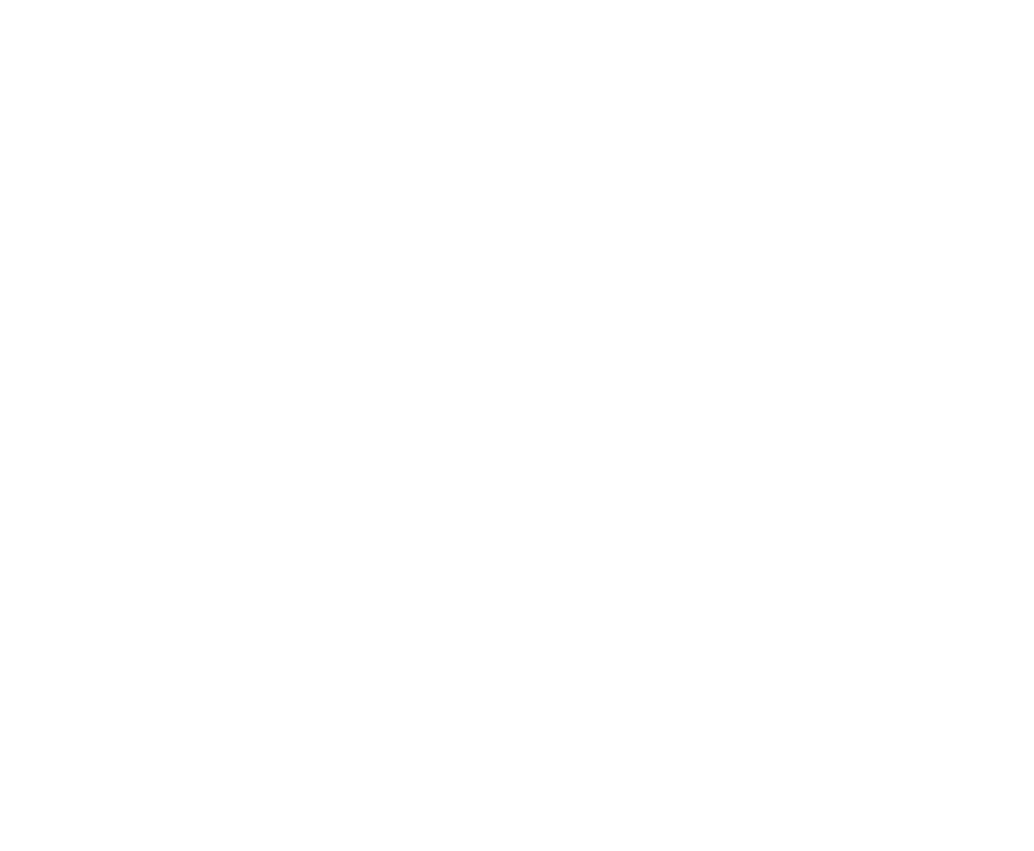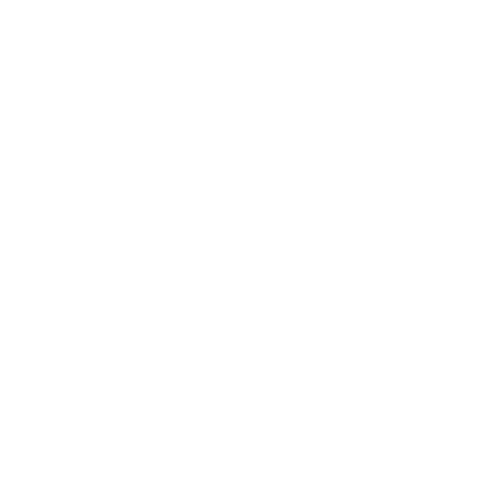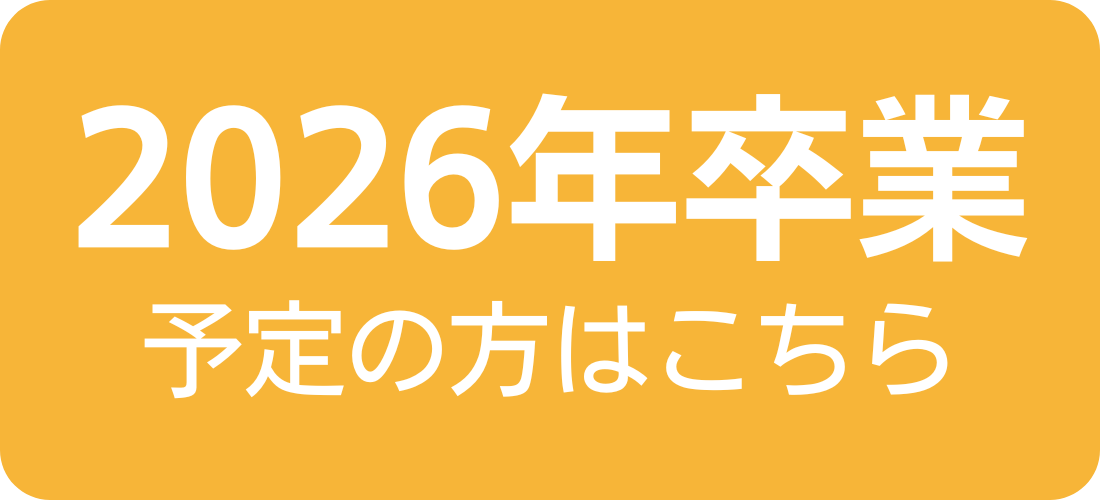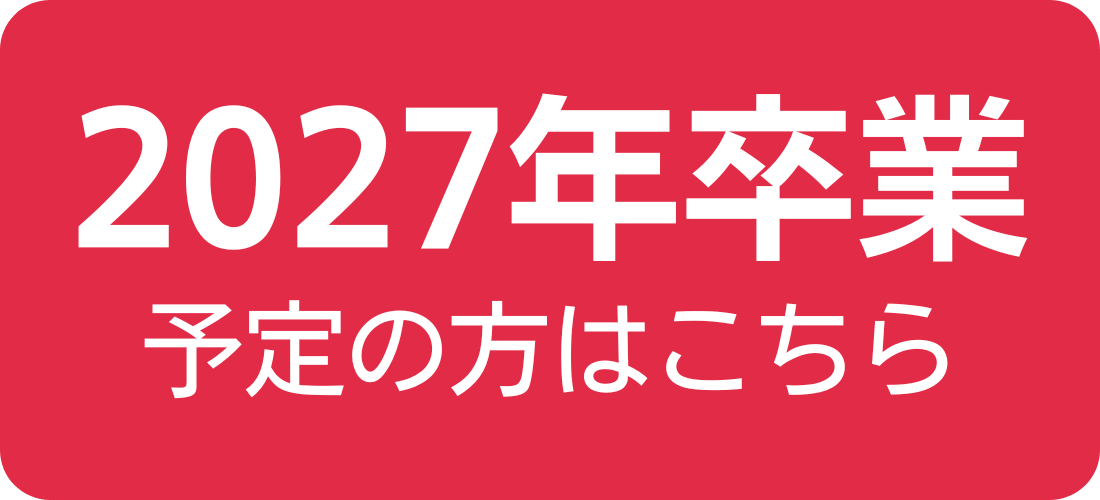目次
面接でよく聞かれる「大学生活を通して学んだことを教えてください」「学生時代に力を入れて取り組んだことは何ですか?」という質問。
これは頻出質問であり、就職活動の採用・面接担当者はこの質問であなたの価値観を見極めようとしています。
部活動に所属している体育会学生のみなさんは、部活動に関する話をすることが多いでしょう。自分の経験したエピソードをもとに伝える自己PRは、運動部、文化部問わず、非常に有効なアピールとなります。
部活動を通して学んだことや身に付いた強みのアピールを考える際に、「あれ、周りと被りそうな内容だな…」「説得力が弱い気がする…」「高校時代のほうがアピールできる内容があるんだけど…」と不安を感じている方。そもそも「何を話したらいいのか分からない…」と悩んでいる方へ。
あなたの魅力を上手に伝える答え方や、面接官に好印象を与えるスキルをご紹介します!
企業が「部活動で学んだこと」
を聞く理由 
ES(エントリーシート)や履歴書などの書類作成や面接においても、よく聞かれる「学生時代に力を入れたこと」いわゆる「ガクチカ」。そもそもなぜ面接官はガクチカについて知りたいのでしょうか?質問の意図や知りたい内容をおさえて、面接官に響く回答にしましょう。大手や人気企業の内定を勝ち取るためには、このステップが不可欠です!
性格や人柄、考え方を知りたい
面接官は、限られた面接時間の中でエントリーしてくれた就活生の中から採用する人財を選ばなければいけません。強みや能力はもちろんですが、あなたの性格や人柄を把握したいと思っています。なぜなら、どんな人物か分からなければ採用できないからです。
企業が求める人物像に合っているか知りたい
面接官は、学生の人物像を把握するための質問をしながら、自社の求める人物像にマッチしているかを見ています。どれだけ優秀な人材でも、自社の求める人物像と異なっていれば採用しません。例えば、成長意欲や主体性を求める企業側に対して協調性をアピールしてもあまり響きません。逆も然りです。つまり、企業とのマッチングが一番重要なのです。
コミュニケーション能力を確認したい
これは面接におけるどの質問においても共通しています。質問に対して簡潔に的を射た回答ができるか、論理的に分かりやすく言語化する能力があるか、を見ています。礼儀正しさも、コミュニケーションを取りたいと思わせる1つの条件として評価されるため、回答だけでなく伝え方や振る舞いも重要です。
\ もっと知りたい方はこちら! /
人事が重視するポイントや人柄は〇〇
面接官の意図はおさえられましたか?
相手の意図にあわせて伝えるべき内容がわかったら、例文を読んで具体的なイメージをふくらませていきましょう!
「部活動で学んだこと」
の例文10選
続いては、実際に部活動を通して学んだことの例文を10個ご紹介します!
キーワード別例文
継続力
私はサッカー部での活動を通して、継続力の大切さを学びました。部員80名のチームで全国大会出場を目標に活動していました。私は2年生までレギュラーに入ることができず、Bチームで練習していました。怪我をしたり挫けそうになる時もありましたが、5kmのランニングと1時間の自主練習は毎日欠かさず行いました。その結果、部内で最も体力がつき試合中も走り続けることができる点を評価され、レギュラーメンバーに選ばれることができました。この経験から、小さなことでも継続することで大きな成長に繋がることを学びました。御社に入社できた際には、難しい仕事や壁にぶつかっても諦めずに継続して必ず結果を残します。
リーダーシップ
私は陸上部での活動を通して、リーダーシップの大切さを学びました。全国レベルの選手が集まる陸上部で、キャプテンを務めました。当初は種目ごとに異なる練習メニューに取り組んでいたため、チームとしての一体感が弱いことに課題を感じていました。そのため、練習前と後には必ず部員全員で集合して5分ほどのMTGを設定しました。今日取り組む練習内容や現状の課題、目標を共有し、異なる種目でも参考になるアドバイスがあれば積極的に発言するように促しました。その結果チームに一体感が生まれたことでアドバイス交換が活発になり、成績が伸びるスピードが早くなりました。この経験から、現状を変えるために自分がリーダーシップを取って部員を動かす大切さを学びました。御社に入社できた際には、リーダーシップを発揮して、会社全体の利益向上に貢献します。
チャレンジ精神
私はテニス部での活動を通して、チャレンジ精神の大切さを学びました。部員7名の少人数で活動しているテニス部のため、新入部員の獲得が課題でした。私が3年生になり新入生勧誘を行う際に、従来のやり方とは全く違う勧誘方法に取り組みました。まず、Instagramのアカウントを開設し、練習のスケジュールや新勧イベントの案内を行いました。また、部員の母校に連絡を取り、高校生向けに勧誘会を行いました。この取り組みによって、その年は10名の新入部員を獲得することができ、なかにはテニス部に入るために〇〇大学への受験を決めてくれた人もいました。この経験から、新しいことにも積極的にチャレンジする大切さを学びました。御社に入社できた際は、チャレンジ精神を活かして新しい業務にも積極的に取り組んでいきます。
課題解決力
私は剣道部での活動を通して、課題解決力の大切さを学びました。全国経験者が多く集まる部で、レベルの高い練習に取り組んでいました。しかし、団体戦では入賞できないことが課題でした。原因は、個人の結果やスキルを重視する部員が多く、団体戦へのモチベーションが低いことにあると考えました。私は、団体戦の楽しさを感じてもらうために、非公式な大会も含めて団体戦形式の大会へ積極的にエントリーしました。また、大会後に食事会を開催し、意見交換の場を作りました。その結果、チームで戦うことの大切さや楽しさを実感する部員が増え、チーム力が向上し、引退試合となる団体戦で優勝することができました。この経験から、課題の原因を明確にして、解決に向けて行動する大切さを学びました。御社に入社できた際には、課題を探り正しい解決策に取り組むことで、着実に成長していきます。
柔軟性
私はダンス部での活動を通して、柔軟性の大切さを学びました。中学から習っている部員もいれば、大学から始める部員も一定数いるため、部員間で競技レベルの差がありました。競技レベルの差がモチベーションの差にも繋がっていることが、部の課題でした。全員が同じメニューを行っていましたが、大学から始めた部員にはレベルが合っていないことに気づき、メニューの見直しを行いました。勝つためには高度な練習が必要だと思っていましたが、チームの底力を上げるために、基礎練習も取り入れることにしました。その結果、ミスが減り、チーム全員で連携プレーができるようになったことで、試合でも勝てるようになりました。この経験から、固定概念に捉われず、臨機応変に対応する柔軟性の大切さを学びました。御社に入社できた際には、持ち前の柔軟性を活かしてお客様の課題解決に取り組みます。
部活動別例文
アイスホッケー部
私は【現状に満足せず、できることを探して周囲と共に挑戦していく力】を、大学生活を通して打ち込んだアイスホッケー部のマネージャーの経験によって身に付けました。我が部は約30名と小規模なチームで、入部直後のマネージャーの仕事が給水やビデオ撮影などの、練習の補助だけとなっていた中、私は「マネージャーの活動幅拡大」に努めました。自分たちがプレーヤーと同等に部活に打ち込み、活動環境改善に尽力することでチームの勝利に貢献できるのではないかと考えたからです。同期や先輩の協力を得て話し合った結果、実施したのは以下の3つです。
①SNS広報(毎試合のLIVE配信)
②練習補助レベルの向上(勉強会の実施、他チームとの情報共有)
③支援金20%増額のためのOB交渉
以上の結果、①が選手のモチベーション向上に、②と③が練習の質向上にそれぞれつながり、連敗続きだったチームが初勝利を挙げることができました。この経験を通して、マネージャーというサポート役ながらも、熱意を持って自分にできることを探し、組織に貢献しようと挑戦する姿勢が身に付きました。貴社に入社できた際にも、組織へ貢献しようとする気持ち、そして社会に貢献しようとする強い想いを持ち続け、自分にできることに挑戦し続けたいと考えます。
詳細はこちら:https://know-how.sponavi.com/entrysheet-2/1229/
バレーボール部
私はバレーボール部に所属し、リーグ戦での優勝を目標に練習に取り組みました。チームとして技術力はあるものの試合で実力を発揮できない選手が多く、セットプレーが乱れて得点ができないことが課題でした。そこで、練習中も試合を意識して、セットプレー前の話し合いや声かけを行いました。また、1点ごとに何を考えてそのプレーをしたのか共有したり、週1回だったMTGを毎日行うようにしたりして、コミュニケーションを取る機会を増やすようにしました。その結果、チーム全体の練習に取り組む意識が変わり、大会本番も連携の取れたプレーをすることができました。目標である優勝は叶わなかったものの、この経験からコミュニケーション能力を身に付け、チームの成長に貢献する大切さを学びました。
詳細はこちら:https://know-how.sponavi.com/how-to/2233/
野球部
私は、部員100名を超える野球部に所属し、選手コーチとしてメンバーのサポートに努めました。メンバーとして試合で活躍するために2年生まで努力してきましたが、チームとして勝つために選手コーチとしてサポートに回ることを決めました。メンバー入りするために努力した経験をもとにメンバーの気持ちに寄り添い、精神的な支えになりました。また、技術力向上のために、動画撮影や試合結果の見直しによってメンバー1人1人の分析を行い、数字に基づくアドバイスを行いました。その結果、リーグ戦で過去最高の成績を残すことができました。この経験から、個人の成長や結果だけにこだわるのではなく、チームに貢献する喜びを学びました。
詳細はこちら:https://know-how.sponavi.com/how-to/2100/
テニス部
私は、テニス部に所属していました。強豪校出身者がおらずライバルとなる同期もいませんでしたが、個人戦でベスト4に入ることを目標に掲げ、日々の練習に取り組みました。まずは試合を分析して苦手な展開を把握し、その展開が得意な先輩にアドバイスを求めました。社会人でテニスを続けているOGの方にお願いし、クラブチームの練習にも参加させてもらいました。その結果どの展開でも有利に立つことができ、最後の大会で3位に入賞できました。この経験から、現状把握と正しい努力をする大切さと自分で考えて行動する主体性を身に付けました。
詳細はこちら:https://know-how.sponavi.com/how-to/2132/
アメフト部
私の強みは、臨機応変な対応力があることである。私は現在、アメリカンフットボール部に所属しており、部員約100名、関係者500名以上の元で主務を務めている。仕事内容としては、司会・試合の運営等人員配置から、電話対応・資料作成の事務作業など様々である。「勝利」に向けて部全体が足並みを揃えていけるよう部員の管理を行うのだが、約100名もの部員が居れば、当然モチベーションの差や価値観は様々であった。そのため、部を運営する中で、批判やすれ違い、トラブルなど大組織ならではの課題と衝突することもあった。初めは戸惑いもあったが、前主務の先輩方にアドバイスをもらいながら、感染症への対応等を通して一つ、二つ先のことを見越し、状況に応じて判断する力を身につけてきた。社会に出た時に、主務を通して身に付いた対応力、大組織を動かすプレッシャーに打ち勝つ心は必ず活かすことができると確信している。
詳細はこちら:https://know-how.sponavi.com/entrysheet-2/1217/
※例文は面接時の話し言葉を想定して「御社」と記載しているものもあります。書類作成時は「貴社」と書くように注意しましょう
※語尾は文章内で統一していれば、「ですます調」と「だである調」どちらでも問題ありません。
他にも、バスケ・バドミントン・卓球・ソフトボール・バレーボール・弓道などさまざまな競技の自己PRや例文があります。ぜひ読んでみましょう!
\ もっと知りたい方はこちら! /
【例文付き】競技別自己PRの書き方
【解説付き】選考通過ES集
例文を読んでみて、なんとなくイメージが湧きましたか?
「自分とマッチする例文がなかった…」
「まだぼんやりとしかイメージできていない…」
という方は、部活動で学んだことのキーワード一覧をチェックしてみましょう!
「部活動で学んだこと」
のキーワード一覧
ここでは、部活動で学んだことのキーワードを役割別にご紹介します!
役割別キーワード
部長(キャプテン・主将)
部長は、部の代表という立場で部員をまとめる役割を任されています。年間スケジュールや練習メニューを決めたり、部内の問題解決に努めます。そのため、リーダーシップを取って物事を主体的かつ戦略的に進める実行力を学んだ人が多いでしょう。
「リーダーシップ」「実行力」「主体性」
副部長(副キャプテン・副主将)
副部長は、部長のサポートをしつつ、部全体に目を向けて状況に応じて動く役割を任されています。部長にも様々なタイプがあり、部長のタイプに合わせた行動や環境に適応する力も求められます。そのため、部の雰囲気や状況を把握しながら仲間とコミュニケーションを取るチームワークや協調性の大切さを学んだ人が多いでしょう。
「協調性」「チームワーク」「状況把握力」
マネージャー
マネージャーは、選手をサポートする役割を任されています。基本的には決められた固定の雑務が多くなりますが、選手一人ひとりの悩みに合わせたサポートも求められます。そのため、選手の力になるために常に気を配り、自分にできることを考えるホスピタリティーや選手との信頼関係の大切さを学んだ人が多いでしょう。
「ホスピタリティー」「信頼」「気配り」
\ マネージャーの人は、これも必見! /
【マネージャー】仕事内容や役割をわかりやすく紹介
主務
主務は、大会申し込みや練習場所の確保など、手続き関係の事務作業を行う役割を任されています。手続きを怠ると、大会に参加できないなど部に甚大な影響をもたらします。そのため、スケジュールを調整しつつ計画的に作業を進めて、ミスなく完了する責任感を学んだ人が多いでしょう。
「調整力」「計画性」「責任感」
広報
広報は、部の活動内容や大会結果などを発信する役割を任されています。OBOGなど卒業生に知ってもらうためだけでなく、部と関係のない人にも知ってもらい応援してくれるファンを増やすことや、新入部員獲得に向けた部の認知度向上、遠征費用の支援金集めなども求められます。そのため、部のブランディングをしつつ、より発信力を強める方法にチャレンジする大切さを学んだ人が多いでしょう。
「ブランディング力」「チャレンジ精神」「発信力」
5つの役割別キーワードをご紹介しましたが、「特に役割は与えられていなかったけど、何をアピールしたらいいんだろう…」という人もいるでしょう。
安心してください。役割がなくても大丈夫です。
面接官は、過程(プロセス)を重視しています。役割がなくても、大学時代の大半を費やした部活動から学んだことはたくさんあるはずです。あなたが感じた大変だったこと、頑張ったこと、成長したと感じることを振り返ってみましょう。きっと様々な苦労や挫折を経験し、それを乗り越えてきたはずです。
「目標達成力」「周囲を巻き込む力」「マネジメント力」「判断力」「忍耐力」「提案力」「困難に立ち向かう姿勢」「失敗を学びに変える力」など、自らの経験をもとにキーワードを考えてみましょう。
よく聞くキーワードではなく、自分でキャッチコピーを考えるのもおすすめです。周りと差別化を図ることができます。
キーワード一覧をチェックして、なんとなくイメージが湧いてきたら、実際に書いてみましょう!
続いては、部活動で学んだことの構成やポイント、注意点をご紹介します!
「部活動で学んだこと」の書き方

早速書き始める前に、まずはどのような構成で書くと相手に伝わりやすいのか、ポイントをおさえましょう!
文章構成
===============
①結論(部活動を通して学んだこと)
②具体的なエピソード
➂今後への活かし方
===============
①結論
どんな質問に対しても共通していえることですが、まず初めに結論から伝えましょう。どの順番で話すかで伝わり方に差が出ます。アピールしたい!という気持ちから、つい部活動の状況や大会結果なども付け加えたくなりがちですが、ぐっとおさえて簡潔に伝えることが大事です。
例)私は硬式野球部での活動を通して「組織に貢献する重要性」を学びました。
②具体的なエピソード
ここでは、部活動の状況・直面した課題・課題に対して行った取り組み・結果の4点を意識して伝えましょう。部員数や競技レベル、役職といった部活動の状況。部活動に取り組む中でぶつかった壁や課題。その課題に対して、解決するためにあなたが取り組んだことや工夫したこと。あなたの行動によって生まれた変化や得られた結果。この4つの項目を数字や第三者の意見も盛り込みながら伝えることで、納得感のある内容になります。チームメイトとの関係性や、後輩への指導などもエピソードに加えると良いでしょう。サークル活動とは異なる、部活動ならではの経験をアピールしましょう。
例)部員数100名を超える野球部の部長として、リーグ戦優勝に向けて取り組んでいました。その中で部員によってモチベーションに差があることに気が付きました。モチベーションを上げるために、100名の部員1人1人と週1回の面談を行いました。また、レギュラー入り以外にも張り合いがでるように、役職を増やして頑張っている人を任命しました。その結果、リーグ戦で優勝はできなかったものの、途中退部者0名で最後までチームとして団結して戦うことができました。
➂今後への活かし方
取り組みの結果から学んだことと、どのように仕事に活かすことができるのかを伝えましょう。まだ働いたことがない学生のみなさんは仕事やキャリアアップのイメージが難しいかもしれません。エピソードは実際の場面がイメージできるように、今後への活かし方はエピソードを通じて学んだことをどのように活かすのかの意気込みとして、記載してみてもいいかもしれません。
例)この経験から、周りに働きかけてチームの結果に貢献する重要性を学びました。仕事においても、自分の結果だけを追い求めるのではなく、周りと切磋琢磨しながら全体の成長や成果の拡大に貢献していきたいです。
ここで紹介した文章構成は、志望動機にも応用できます。伝わりやすい文章構成がわかると、なんとなくイメージが湧いてきた人も多いでしょう。
ただし、文章構成以外にも重要なポイントが3つあります。より合格に近づくためのポイントはこちら!
「部活動で学んだこと」のポイント

よりあなたの経験を魅力的にアピールして、内定に近づくためのポイントをご紹介します!
ポイント
過程が重要
優勝などの輝かしい実績や受賞経験などの結果ももちろん大切ですが、努力してきた過程も重要です。なぜなら、部活動で結果を残せたからといって、仕事でも結果を残せるわけではないからです。結果を残すまでの過程から、仕事にも活かせて活躍してくれそうなポテンシャルを見つけて、面接官は採用を決めます。結果だけでなく、日々の努力など過程の部分をしっかり伝えるようにしましょう。
再現性をイメージさせる
過程を伝えることと繋がってきますが、仕事でも再現できる強みを身に付けていることが重要です。部活動も、部という1つの組織での活動です。その中で身に付けた強みは、会社という組織でも発揮できる可能性が高いです。部活動を通して身に付けた強みを、社会人になって職場でどのように活かすことができるのかも、しっかり伝えるようにしましょう。インターンシップの経験があれば、それをふまえて話すのも良いでしょう。
エピソードを複数準備する
業界や職種によって求める人物像は異なります。そのため、選考を受ける先によってエピソードを変えることで、より効果的に面接官へアピールすることができます。嘘をつくのはいけませんが、部活動を通して学んだことや身に付けた強みは1つではないはずです。どんなに些細な事でも大丈夫なので、複数のエピソードを準備しておくようにしましょう。事前に企業研究をしっかり行うことも大切です。
構成やポイントをおさえて、面接官に響く回答を作る方法はわかりましたか?
続いては、回答内容やイメージが固まってきた方向けに、最終チェックとして注意点をお伝えします!
「部活動で学んだこと」の注意点

魅力的な経験や学びがあっても、伝え方1つでマイナス評価になってしまうこともあります。そんなマイナス評価に繋がってしまうリスクを減らすために、注意点をご紹介します!
注意点
①専門用語はなるべく使わない
体育会系の人やその競技を知っている人しか分からない言葉は使わないようにしましょう。一般的に知らない用語が出てくると、話を理解しづらくなります。用語の説明を求める質問が入ると、他にアピールしたい内容を伝える時間もなくなってしまいます。専門用語は使わず、分かりやすい表現に変えるか、簡単な説明を付け加えるようにしましょう。
➁嘘をつかない、話を盛らない
部活動で学んだことを伝える際に大会結果や成績を伝える人も多いでしょう。その中で、ついエピソードや数字を盛ってしまいたくなることもあるかもしれません。しかし、嘘は必ず気づかれます。毎年何人も面接している面接官は質疑応答を通して深掘りをするため、嘘をつくとどこかで回答に矛盾が生じ、ばれてしまいます。あなたが部活動で得られた経験はかけがえのないものだと思います。自信を持って実体験を話しましょう。
➂話し過ぎない
面接官にアピールするためにあれもこれも一度に話してしまうのはNG。話にまとまりがなくなったり、自慢のように聞こえたりしてしまいます。アピールしたい気持ちは分かりますが、ぐっとこらえて簡潔に話すようにしましょう。その際に、深掘りしてほしいポイントはあえて抽象的に話すことで興味を持ってもらう、というスキルもあります。深掘りされることを前提に会話形式で想定質問と回答を準備しておくと、実際の面接でも余裕をもって話すことができます。「苦手だから仕方がない」とあきらめずに、しっかり準備と対策をしましょう。
\ もっと知りたい方はこちら! /
面接で合格する話し方のコツ
「注意点も確認したしこれで大丈夫!」という方、ちょっと待ってください!
セルフチェックで終わらせるのは非常にもったいないです。就職課や友人、先輩など、必ず第三者からアドバイスをもらいましょう。
「就職課に行く時間はないけど、誰かに添削してほしい」「協力してくれる人が見つからない」「専門的なアドバイスがほしい」という人は、エージェントやアドバイザーなど就活のプロを頼ってみましょう。初めて経験する就活の中で、プロのサポートはとても心強く頼もしい力になります。
自分では完璧だと思っていても、相手によっては理解しづらい表現もあります。アドバイスを聞いて内容を改善することで最初より良い回答になり、選考通過率もUPします。アドバイスをもらったり、足りないポイントを指導してもらうことは、メリットしかありません!ChatGPTなどのツールもありますが、生身の人間の視点からのフィードバックは非常に重要です。
最後に、ここまで読んでくれたあなただけに、おすすめの㊙テクニックをご紹介します!
内定が近づく㊙テクニック

「部活動で学んだことを上手にアピールして就活を成功させたい!」という体育会学生におすすめのサービスは、『スポナビ』です!
スポナビ
スポナビは体育会学生に特化した就活支援サービスで、自己分析や業界企業研究、イベント情報やおすすめ優良企業の紹介、面接対策、書類添削などの就職活動に関するサポートが完全無料で受けられます。
就活のプロであるスポナビのスタッフは体育会出身者が多く、1年を通して大学や部活を担当します。そのため、自分自身の経験をもとに同じ視点で体育会学生に寄り添い、各部活動のスケジュールや特徴を把握したうえで、内定獲得そして納得のいく就活をトータルサポートします。
面談の中で、自己PRやガクチカなどのES添削も行っています。ESなどの書類を添削してもらうための面談は、Webなどのオンラインでも対面でもどちらでも参加可能です。文章が完成していない状態でも問題ありません。すでに提出したエントリーシートの添削も可能です。1対1でじっくり話しながら一緒に解決策を探していきます。基本的には面談で添削を行っていますが、まとまった時間を確保することが難しかったり住んでいる都道府県内にスポナビのオフィスがない就活生に対しては、LINEで添削することも可能です◎
《LINEの添削例》
このような感じで気軽に添削してもらうことができます。

\スポナビの活用例を読んでみよう!/
元スポナビ学生に聞いた!活用のコツ
スポナビ学生のリアルな就活体験談
体育会学生は『時間』が限られているため、使えるツールやサービスは積極的に使って就活を効率良く有利に進めましょう。就職課とスポナビなどを併用することもおすすめです。
「就活に対して漠然とした不安がある…」
「大手企業や有名企業に受かるコツを知りたい!」
「面接対策・面接練習をしてほしい!」
といった質問・悩み相談・各種依頼も大歓迎です◎
「何を聞けばいいか分からないけど就活の情報を知りたい!」という声にもお応えします!